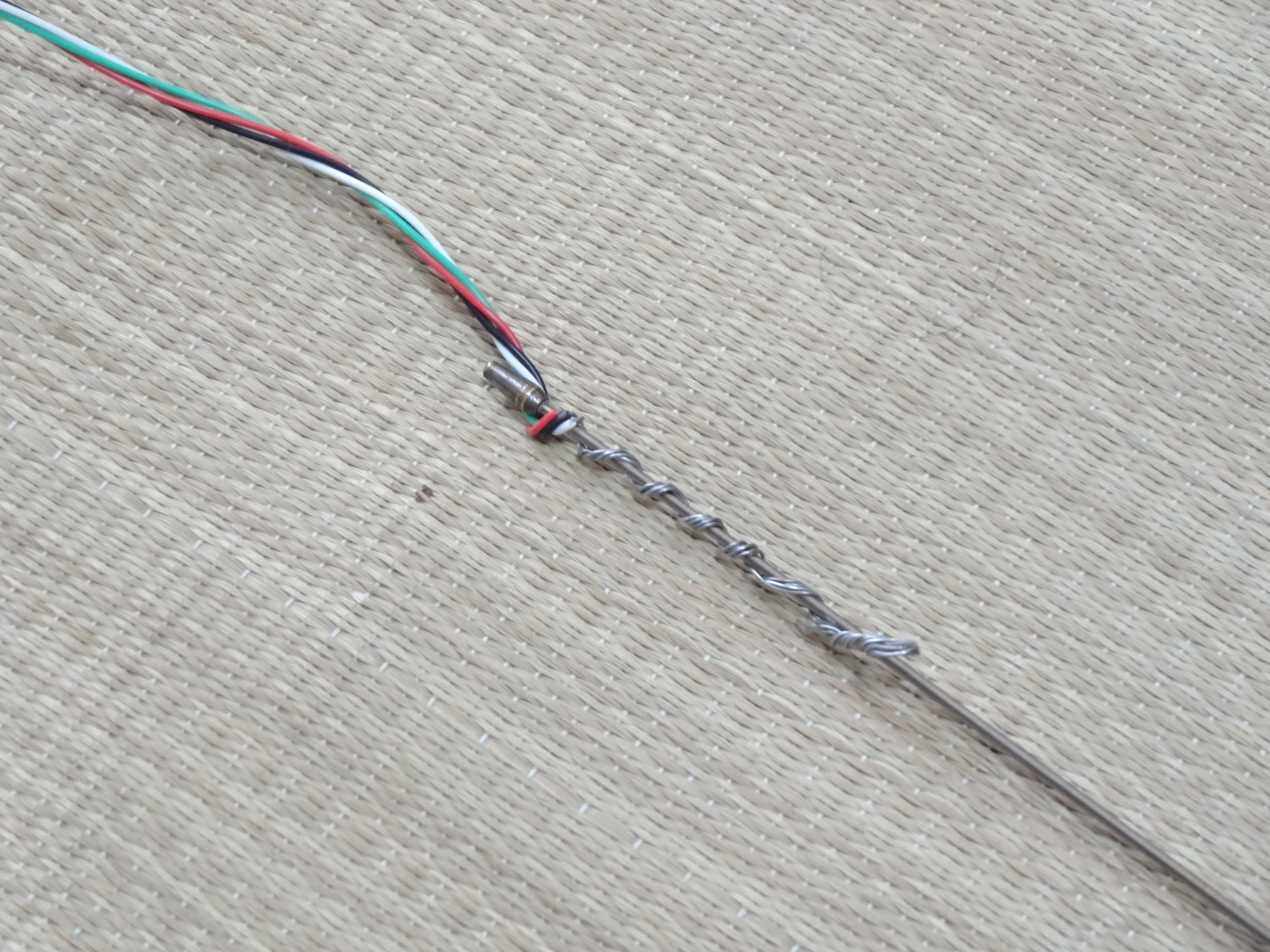★「・・・高周波な生活(の一部)」トップページへ戻る★
★アパマンハムのアンテナ実験??へ戻る★
このページは・・・
since 2022/09/25 初期ページ作成
update 2022/11/09 14MHzでの成果を追加
update 2023/06/04 再調整する事に
「・・・高周波な生活(の一部)」
第一電波工業製 MD200+MDC6 で14MHz帯に出る
MD200の改造というか・・・付け足し?(笑)
★昔購入したダイヤモンドアンテナの【MD200+MDC6】。
移動運用で現地へ行く途中で6mバンド内コンディションチェックや、
移動先でのサブアンテナで大活躍した。
後から「車の中からHFも出てみたい」ということで「MDC217」も追加。
★その後 2016 年に単身赴任を喰らってからは、
自宅とアパート間の往復移動中に航空無線(HF帯洋上管制)受信や、
秋田のアパートでベランダアンテナとして活躍。
(そして積み替えが面倒になりヤフオクで中古MD200を一本追加)
★2021年7月に変更になった単身赴任先・盛岡のアパートでも、
ベランダアンテナとして大活躍中。
メニュー(?)
1.発端w
2.検討して実験
3.実際の成果(2022/9/25当初)
4.実際の成果(2022/10/9,11/9追記)
5.全体的に再調整する事になった(2023/6/4追記)
発端
●国内コンテストで賑やかな時期なので、
愛・地球博コンテストに14MHzで参加してみた。
アンテナはベランダ突き出し設置の 超短縮V型DP【CHV-5α】で。
(7MHz帯は電灯線由来のパルスノイズで断念)
●9/22夜9時の開始直後から深夜まで、国内局は聞こえず。
(まぁ国内スキップ時間帯だしね)
9/23朝6時から再チャレンジ。あれ?全然聞こえないよ?
聞こえる信号はS0~2位で激弱、当然いくら呼んでもダメ・・・
今すぐ、この14MHzの状況を改善するには?
(ここからしばし、脳内検討・・・)
●今から14MHzのDP作るか?
つーても、ベランダの幅は1/2λの10mも無いぞw
●じゃあ14MHzの1/4λGPはどうだ?
うーん、手元に5mもの非金属なポールは無い・・・
●ベランダ手摺に固定のMD200は単体で全長約2m位。
14MHz帯1/4λの約5.1m(波長短縮率込み)に【3m位足りないだけ】だなぁ。。。
●じゃあ・・・【 MD200+MDC6 】の状態で、
全体で14MHzに同調する様に3mの電線を接続で、ほぼ1/4λのフルサイズだな。
CHV-5αで3.5MHz帯に出たのと同じで、延長電線付けてしまえ。
●MDC6自体は電気的(高周波的)には、エレメント下端とアース間に
50MHz付近に同調してるLC並列共振回路がある「だけ」だから・・・
14MHzなら無視出来だろ。
無視しよ(笑)。
(ここまで約3分の脳内検討終了w)
<1>
速攻で実験開始。
CHV-5α用に作った、【 3.5MHz用延長エレメント 】と同じ方法!
使用電線は当然同じで、「0.5-4TJVカロクミ・ジャンパー線」 を使用w。
とりあえず(接続用の加工余長込みで)3.3mくらいに切り出し、接続。
(この先の画像はクリックで実寸大表示されると思う)
<2>
でも、コレじゃ後々面倒じゃん。
MDC217使って7MHzで記念局とか特別局追いかけるのにも使ってるし。
毎回巻き付けてたら、絶対金属疲労で電線が切れるし。
と、色々考えながら先端部分を眺めていて気がついた。
「あれ?ギボシ端子と同じ位のサイズじゃね?」
並べてみたら形まで似てるという。。。
<3>
ギボシ端子を半田付けして、完成。
前作CHV-5α用3.5MHz用延長エレメントと同様に
先端部分を折り返して調整。
折り返し部分をループ状に広げてあるのがポイント。
全長を変えずにループを広げたり狭めたりで、
同調点が動くのではないか?と思って試してみただけ。
キャパシティハットと一緒やね(笑)
<4>
CHV-5aの時と同じく「nanoVNA」で計って調整して・・・ビンゴ!!
開発者のTT@北海道(edy555)氏!ありがとう!
長さを大雑把にあわせてから、
先端ループ幅で微調整したのが下の画像。
SWRは高く、約2.0だけど一応同調してるって事で。
SWRが高い原因はホットとコールド間に、
50MHzのLC並列共振回路があるから?
にしては、スミスチャートの値[584pF]が・・・?
下側だから「-jX」だから~容量性リアクタンス。
簡単に言えば「C」が直列に入ってるって事、だよな?
nanoVNAの表示@14MHz帯。
(center=14.1MHz,span=2MHz,SWR scale=1)
(いちおー脳内検討・・・)
・一応、モービル基台は鉄骨製ベランダ手摺と
直流的に接続されているけど高周波的には怪しいのか?
・カウンターポイズを7MHz用1/4λにして接続しているから?
・いやいや、先ずは・・・・・
『 先端をループにしないで電線長を調整しろ! 』 と。
『 スミスチャートで-jX言うてるんだからキャパシティハットもどきは不要だろう! 』と。
(約3分の脳内検討終了w)
短縮ナシの1/4λエレメントなので、
画像のとおり帯域幅はかなり広そう。
同調していない電線より、同調している電線の方が確実に良い。
うーん・・・取りあえずこのままで!
外部チューナーで反射を抑えてコンテスト継続する!!
この時点で9/23,09時JST過ぎてたのでコンテスト参加を優先。。。
<5>
運用状態での全景。
人目を気にして愛・地球博コンテスト&福岡コンテスト終了後、
9/25の夜にコッソリ撮影したw
通行人の目が気になるだけでなく、
追加電線の先端から地上まで約2mという低さなので、
コンテスト時以外は夜間だけ接続するという運用で行こう。
14MHzでの成果(2022/09/25)
・14MHzでほぼ短縮ナシの1/4λ逆L状態。
横に設置してあるコメットのCHV-5aより全然良い。
水平/垂直系の差もあるとは思うが、
CHV-5aでS1~S2の信号が一気にS9+まで上がる。
(当然応答率も良い)
・但し、コンディションによって、
状況が逆転する事が「たまに有った」ので、
CHV-5aと切り替えながら運用した。
・14MHzオンリーで参加した、
第17回愛・地球博記念コンテスト(9/22~23)と
第16回福岡コンテスト(9/24~25)ではそれなりにQSO出来た。
ANT別QSO比率は、「CHV-5aノーマル」:「MD200+延長エレメント電線」で2:8位。
・ジャンパー線なんか使わずホームセンターで切り売りしてる、
0.5mmSQのKIVビニル電線(撚り線)を使えば良いんじゃ?
そっちのほうが軽くないか?と思いついたのは、
上の写真を撮影してから延長エレメントを外している時(笑)。
・当然ながら、同じ方法で10/18MHz帯も対応可能と思われる。
24MHz帯は波長的にダメかもしれない。
(MDC6を外して直結なら別)
でも現状では、あまり興味がない。
(ローカルコンテスト好きなのでw)
2022/10/09追記:
・10/8~9の全市全郡コンテストにC14Mで参加。
前年スコアと比較すると10位以内くらい・・・な、得点で満足。
2022/11/09追記:
・このMD200+MDC6+延長エレメント電線の構成で、
2022/10/25~11/9に行われたDX-Pedi、
パプアニューギニアの「P29RO」ともCWでQSO成立。
2023/6/4追記:
全体的に再調整してみる事になった(笑)
初夏になってCondxも良くなり、
50MHzではほぼ毎日、宮崎のJA6YBRビーコンが聞こえる♪
2023/6/3~4に開催される「第47回宮崎コンテスト」へ
「50MHzで」参加しようと準備してて・・・の巻。
<6>
今日もYBRビーコン聞こえるけどQSB激しいなぁ。
MD200+MDC6は、そのままベランダ設置のままで、
HF6CLをベランダ反対側のアパート玄関側に仮設して、
お空の状態に合わせて状況良い方に切替運用しよう!
・・・とか、6/3(土)の朝に思いついた。
(宮崎コンテストは18:00開始だからノンビリ準備)
<7>
HF6CLは50.2MHz位でSWR落ちてるのを確認。
ノンラジアルらしいし、最初に調整してからあまり変わらない。
で、MD200+MDC6を確認してみたら
「肝心な所のSWRが・・・!」
(というわけで記録を開始した・・・)
その時の、nanoVNA表示@50MHz帯。
(start=50MHz,stop=51MHz,SWR scale=0.1)
なんでこんな事になってんの?w;
この状態で「延長エレメント電線を接続した14MHz帯」は、
前出<4>と大差なしなので割愛。
<8>
とりあえずMDC6を調整。
調整前↓
調整後↓
なんでこんなに位置がズレた?
ベランダ内カウンターポイズ電線は2本で、7MHzの1/4λ長で作った物。
1本は伸ばしきってベランダから外の外壁に沿って地上へ垂らし、
1本はベランダの床面に乱雑にグネグネさせていた。
そういや・・・
「今年度も始まったJARLのQRPデー特別記念局、7MHzなら出来そう!」
と、思いついた。
んで、MD200+MDC217による7MHz帯での特性upを狙って、
グネグネしてた1本も床面をベランダの端まで真っ直ぐ延ばし、
行き止まりで給電側に折り返した。。。
それの影響くらいしか無いな、これは。
ちゃんとカウンターポイズになったって事?(苦笑)
以下は調整後のnanoVNA表示@50MHz帯。
(start=50MHz,stop=51MHz,SWR scale=0.1)
最良点50.3MHzでSWR=1.23、50~51MHzでSWR=1.4以下。
<9>
そうだ。もしCondx悪いときは14MHzにも出よう。
というか、MD200+MDC6の状態が変わった んだから、
当然
「延長エレメント電線を接続した14MHz帯」も特性変わってる んじゃね?
というわけで、前出<3>の電線を接続してみた所・・・
いきなりSWR下がってた(苦笑)
やはり7MHzの1/4λカウンターポイズ(というかラジアル線?)、
2本目もちゃんと伸ばしたのでアース効果が出てる?
以下は前出<3>の電線を接続しただけ状態。
SWR最低点が低い所へ移動していた。
nanoVNA表示@14MHz帯。
(center=14.1MHz,span=2MHz,SWR scale=1)
電線先端のループ状部分を小さくし、
その分電線自体も少し切り詰めてみた。
以下は延長エレメント電線の長さを微調整後の、
nanoVNA表示@14MHz帯。
(center=14.1MHz,span=2MHz,SWR scale=1)
14.1MHzでSWR=1.5以下、
14MHzのバンド内SWR=2.0以下になった\(^-^)/バンザーイ
(でもスミスチャートの「1.01nF」が気になる・・・orz)
・なお、nanoVNAでの測定点は全て、
ベランダ固定「モービル用基台コネクタ直づけ」の、
3D-2V約5mの先。
・実際の運用状態は、更に5D-2V約5mで延長し無線機群へ。
・アパートの建物(鉄筋コンクリート3階建て)に接近してる割に、
一応1/4λフルサイズで動作しているのか帯域幅は広い。
nanoVNA上で見てもSWR=2以下の帯域は約500kHz位。
(13.9~14.4MHz位に見て取れる)
・実際に無線機へ接続しSWR計で計っても、
14.000~14.350MHzの間はSWR=2以下。
2023/6/4 (コレを編集してる夜11時・・・)
・ちなみに、発端?となった「第47回宮崎コンテスト」、
50MHzは不安定なコンディションで2局QSOでおしまい。
結局、「MD200+MDDC6+延長エレメント電線」で14MHzで参加w
また文章だらけのページを書いてしまった・・・・・
そのうち、ちゃんと延長エレメント電線を切り詰めて合わせてみようw
★アパマンハムのアンテナ実験??へ戻る★
★「・・・高周波な生活(の一部)」トップページへ戻る★
管理用:このページのURLは、 https://caiman0223jp.ifdef.jp/ant/md200-1.html